 |
 |
 |
 |
| 梅雨時の頃にはしっとりと美しいアジサイ(紫陽花;アジサイ科)の花が随所に見られます。「こころをばなににたとへん こころはあぢさいの花 ももいろに咲く日はあれど うすむらさきの思い出ばかりはせんなくて(以下略)」という荻原朔太郎の詩にもあるように、花の色がいろいろと変化します。 |
アマチャ(甘茶;アジサイ科)です。 アマチャの名は葉を乾燥させると甘くなって甘茶をつくることからきています。甘味が強いので砂糖代わりの甘味料や歯磨きの甘味、醤油の味付けなどに用いられています。 |
ユキノシタ科の多年草ユキノシタ(雪の下)です。ほの暗い湿地や石垣などに群生しますが、冬に雪の下で枯れずに緑を保っているのでこの名がついたという。花の精が舞い降りたような小さな白花が美しい。 |
バラ科の落葉低木シモツケ(下野)。虫が盛んに花の密を吸っています。細身の葉のうえにこんもりと乗っている雲のような花が美しい。全体がうぶ毛のようなおしべでおおわれて優美な雰囲気を醸し出しています。 |
|
 |
 |
 |
 |
| バラ科の落葉低木キンロバイ(金露梅)。日本では主として高山の岩石地に生える。白い花の品種をハクロバイ(白露梅、銀露梅)と呼びます。なかなか風流な名前ですね。 |
古くから肝臓の薬とされてきたマリアアザミの花です。地中海沿岸原産のキク科の二年草。オオアザミとも呼ばれています。葉に白いまだら模様があるのが特徴。 |
アサツキ(浅葱、千本ネギ;ヒガンバナ科)。日本各地に自生するネギの仲間。アサツキを軽く湯がいて酢味噌などに付けて食べると酒の肴に最高です。 |
青紫、赤紫、白、絞りなどの色とりどりのハナショウブ(花菖蒲;アヤメ科)の花が咲き乱れていて、別世界に来たかのように錯覚する美しい空間です。 |
|
 |
 |
 |
 |
| 元東京医学校の建物を背景にしたハナショウブ(花菖蒲)の池です。この周辺では季節によってウメ(梅)、ツツジ(躑躅)、ハギ(萩)などいろいろな花を楽しむことができます。 |
この季節の面白い林の風景をいくつか紹介します。これは、ハグマノキ(白熊の木、スモークツリー;ウルシ科)。木全体がボヤーっとうす紅く煙っているように見えます。 |
ハナキササゲ(花木大角豆;ノウゼンカズラ科)の白黄色の花が満開です。ちょうどササゲのような形の実をつけるのです。花をよく見るとシャガ(著莪)の花に色合いがよく似ています。 |
暖地に生育する常緑高木のフシノハアワブキ(節の葉泡吹;アワブキ科)。咲き終わった花がぼろぼろと木の上から落ちてきます。地面はおが屑を敷きつめたのように真っ白になります。 |
|
 |
 |
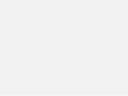 |
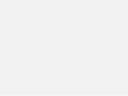 |
| まさに威風堂々の白くて大きなタイサンボク(泰山木;モクレン科)の花です。まるでこの一帯の空間を支配しているような王者の風格があります。 |
ソメイヨシノの実がなっていました。一見ササクランボのようですが、本物のサクランボと比べて小ぶりで、味は残念ながら全然ダメです。 |
|
|
|
  |